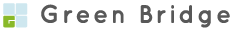目次
この夏の暑さの影響なのか、この時期にしては暖かい日が続いていますね。こんな時こそ冬支度を始めるのにもってこいの時期です。今回は、冬に起きやすい電気火災の特徴と注意点についてご紹介します。
冬の火災に注意
平成29年における建物火災件数は21,365件と前年よりも増加しています。また、火災発生時期については12月〜3月までの冬の間が多く特に注意が必要です。冬に入ると暖房器具を使うから火災が増えるというのも要因としてありますが、意外なところから出火していますのでご自宅や職場の確認をお願いします。
火災の原因は意外なところ
火災の原因で一番多いのがコンロでその件数は2,986件となっています。そして配線器具と電灯電話等の配線からの出火が2,044件とこちらも前年よりも増加しています。
また、平成26年中における家庭電気製品の火災発生状況をみると、電気ストーブが78件、差込みプラグが59件、コンセントが48件、コードが45件、蛍光灯42件、屋内線が40件などとなっています。意外なのが、差込プラグやコンセント、コードなど配線器具からの出火ですが、これが所謂トラッキング現象と言われているものになります。
トラッキング現象の原因と対策
中部電力 ホームページより
トラッキングとは、長い間差しっぱなしになったコンセントと電源プラグの間にはホコリがたまり、そこに加湿などにより発生した湿気が加わることで、電源プラグの刃の間で火花放電が繰り返されることです。
これによりコンセントに接する絶縁部を加熱し、電源プラグの刃と刃の間に“トラック”と呼ばれる電気の道をつくります。
やがてはそこから放電をおこし発火。これがトラッキング現象です。
ホコリがたまる要因

危険なタコ足配線
掃除をしている時、どうしてコンセントの周りに黒ずみができたりホコリが溜まってるんだろうと不思議に思うことはありませんか。掃除機を使った掃除をしていると、床掃除がメインになるので、コンセント周りやテレビの後ろ側など掃除を疎かにしてしまい『コンセントを長期間掃除していない』ことによって、他の部分より溜まっていると考えがちです。
実はそうではありません。『タコ足配線』のコンセントにホコリがたまりやすいのも同じなのですが、電気コードの周りに発生している『電磁波』や『静電気』によりホコリを誘引している事が原因として考えられます。そこで、以下の対策をすぐに実行していただくことをお勧めします。
4つのトラッキング対策
- 使っていない電気器具のコード (プラグ)は、コンセントから抜く
- コンセント周りをこまめに掃除する
- タンスの裏側など、目の届きにくい場所のコンセントはなるべく使わない
- たこ足配線は止める

こまめにプラグは抜く
すぐにできることは、使っていない電気器具のプラグを抜くことです。差しっぱなしにしているだけで電気は流れているし、コードが重なることで熱を発生することもあります。もちろん、歩くときにコードが引っかかり、躓いたり物が倒れたりする恐れがあるので、常に心がけてもらいたいところです。
また、年末の大掃除の時には配線の見直しも合わせて実施しましょう。意外と使っていない電気器具があったり、コードが傷ついていてすでにトラッキング現象の跡がついている場合があります。そんな時は、製品をメーカーや専門業者へ点検に出すことをお勧めします。
これらの対策は、火災を予防するために必要不可欠なことなので必ず実行して下さい。とくに一人暮らしの方は、延長コードでタコ足配線になりがちなので、家電製品の見直しをすすめるといいですよ。
電気火災の予防と省エネ
以下にお伝えする電気火災の予防法は、トラッキング現象の防止とともに、省エネにも役立つのですぐに実践してください。安全な上にお得な方法です。
- 差込みプラグを抜くときは、プラグ本体を持ちまっすぐに引き抜く。
- 差込みプラグはしっかりとコンセントに差しましょう。隙間があるとホコリが入り込みますよ。
- コードの上にはものを載せないようにしましょう。コードに傷がついたり折れたりすると、感電や火災の原因になります。
- むやみにコードを束ねない。コードが過熱して火災を引き起こすことがあります。
- コードを柱などにステップル止めをするのはやめましょう。間違ってコードを傷つける恐れがあります。
- コンセントやコードには、使用できる電気量に制限があります。表示されている電気量を確認して使用しましょう。
- 使わない電気製品のコードは、こまめに抜きましょう。待機電力の消費が抑えられ省エネになります。
家電製品全般に対する注意

オイルヒーターも毎年点検を
季節家電については、長期間使っていない場合が多いと思います。例えば加湿器やこたつ、ホットカーペットや電気ストーブなど。保管状態が悪いとスイッチを入れた途端に煙が出たりショートすることがあるので以下の注意事項を参考に事前点検が必要です。
筆者もオイルヒーターのスイッチを入れた途端にオイルが焼けるような匂いがしたことから、すぐに使用をやめ、新しいものに交換したことがあります。スイッチを入れたまま、その部屋を離れていたら火事になっていたかもしれないと考えると、恐ろしくなりますね。
- 電気製品の取扱説明書をよく読み、異常がないか確認しましょう。
- 故障した場合や調子が悪いと感じた時は、自分で分解せず、専門の業者に修理を依頼しましょう。
- 暖房器具の周囲には、燃えやすいものを置かないようにしましょう。
- 長年使用していなかった電気製品は、使用する前に専門の業者に点検を依頼して、安全を確認してから使いましょう。
まとめ
オール電化住宅は火災リスクが低いと考えがちですが、それはコンロの話だけであって住まいとしては変わりません。場合によっては、全てを電気で賄うので大きな電力が必要になります。その分、建物の中にはたくさんの電気配線が通っていて、特に天井裏などにたくさんの電気配線が入ってます。ホコリが被っていたり配線が痛んでくると火災リスクが高まりますので、定期的な点検が必要になることをお伝えしておきます。
次回は、トラッキング現象の原因となる電磁波対策についてもお伝えしていきます。
問合せ先:株式会社Green Bridge(グリーンブリッジ)→問い合わせフォーム
 住まいや暮らしに関する情報を、メディアやセミナーを通じてお伝えしております。ユーザー様向けのセミナーや企業様向けの講演など各地で行っております。住まいを通じて、お客様に寄り添う、ていねいな暮らしのコンサルタントとしてお客様の快適な住まいと心地よい暮らしをサポートいたします!
住まいや暮らしに関する情報を、メディアやセミナーを通じてお伝えしております。ユーザー様向けのセミナーや企業様向けの講演など各地で行っております。住まいを通じて、お客様に寄り添う、ていねいな暮らしのコンサルタントとしてお客様の快適な住まいと心地よい暮らしをサポートいたします!
株式会社Green Bridge →問い合わせフォーム TEL03-3791-1585
住まいの専門サイトHOUZZでユーザーの家づくりをサポート記事を連載しています。→こちら
運営する暮らしのサロンのセミナーの先行予約もいち早くご案内!
ぜひメールマガジンにご登録ください。